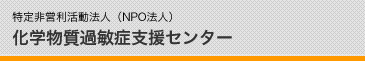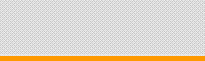会報第3号(2001.10.20)
 |
環境省研究班がMCS調査研究報告書を発表 |
| |
網代 太郎 (CS支援センター事務局長) |
| |
化学物質過敏症の存否などを研究する、環境省調査研究班による「本態性多種化学物質過敏状態の調査研究」の2000年度報告書がまとまり、8月に公表されました。
この報告書の報道発表文は、患者の化学物質曝露試験の結果等から「(症状を誘発する)原因について明確な判断が出来なかった」等と結論づけ、調査研究の継続が必要だと指摘しています。化学物質過敏症について「肯定」も「否定」もしない「中立的」結論のようにも読めますが、報告書を検討すると、もう少し「肯定」へ踏み込んでも良さそうな内容であり、もっと違うまとめ方があったのではないかと、残念です。
なお「本態性多種化学物質過敏状態」は、「(多種類)化学物質過敏症」のもとの英語「Multiple Chemical Sensitivity」を“環境省研究班流”に訳した言葉です。疾患として認められていないので『……症』とは言えないのだそうです。
研究班は、1997年にスタートし、班長は大井玄・国立環境研究所長。これまでに98年度報告書も発表されています。
今回の報告は、化学物質曝露試験と、動物実験の2項目についてです。
このうち、化学物質曝露試験では、患者8人と非患者4人を対象に、北里研究所病院の臨床環境医学センターで低濃度の化学物質を含むガスに曝露させる試験を行い、自覚症状や脳血流量の変化等を調べました。その際、被験者の変化が心因性でないか確認するため、プラセボ(この場合は化学物質を含まないガス)にも曝露させました。
この実験では、患者8人のうち、4人はプラセボよりも化学物質の方がより自覚症状が悪化しましたが、あとの4人は、プラセボの方がより悪化したか、または化学物質とプラセボとで差がありませんでした。非患者では、3人が化学物質とプラセボで差がなく、あとの1人は化学物質の方がプラセボより症状が軽減しました。
患者の自覚症状についての結果が、上記のように真っ二つに割れたことから、報告書は「本病態が化学物質によって誘引されるか否かを判断することは困難であった」(8頁)としています。
この試験で曝露させた化学物質は、40ppbおよび8ppbのホルムアルデヒドなどであり、専門家によると、いずれも患者でも症状が出るかどうかという低濃度です。濃度を上げれば、もっとハッキリした結果が出る可能性もありますが、症状悪化など患者への危険が大きくなります。つまり、自覚症状の変化から、今回の試験結果を評価するのは、あまり意味がないというのです。
報告書は、今後について、対象者数を30人程度に増やす▽今回の対象者に再試験を行い同じ結果が出るかを調べる−などを行うとしています。しかし、対象者を増やしても濃度を上げなければ、今回と同様、ハッキリした結果が出ない可能性もあります。かと言って、濃度を上げると患者への危険が増します。
この点について、環境省環境安全課の担当者に質問したところ「ご指摘はもっともだが、まず対象者を増やして行い、その結果から次の方向性を決めたい」との回答でした。
自覚症状のほかに有効な評価方法の一つとして、北里研究所病院の先生方が開発した、近赤外線酸素モニター検査(NIRO)があります。頭部表面近くの脳血流を調べると、患者が化学物質に曝露した場合に明らかな血流量の変動があり、これが化学物質過敏症の客観的な“証拠”になり得ると期待されています。
環境省研究班の調査でもNIROが採用され、患者は非患者と比べて脳血流量の大きな変動や低下が確認され、今回の報告書も「NIROにおいて、患者群との分類は概ね可能であった」と評価しています。
今後は、患者の自覚症状だけでなく、NIROで得られるような客観的なデータに重点を置いて評価していくことが必要ではないでしょうか。環境安全課の担当者にそう質問したところ「ご指摘の通りであり、現在、これを指標にしようという方向にはある」とおっしゃっていました。この方向で研究が継続され、化学物質過敏症の公認につながるよう、大いに期待したいです。
また、研究班メンバーのほとんどは、実際に患者に接したことがない方です。環境省の担当者に「患者団体等からヒアリングをする予定はないのか」と質問したところ、ないとの答えでした。純粋な学問研究をするうえで、患者等からの訴えを聞く必要はないと考えているのでしょうか?
しかし、疾患が先にあるのではなく、実際に苦しんでいる患者がいて、それを治療するための疾患の特定・分類なのではないでしょうか。研究班の方々には、患者の実態に接する機会を持つよう、お願いしたいです。 |
|